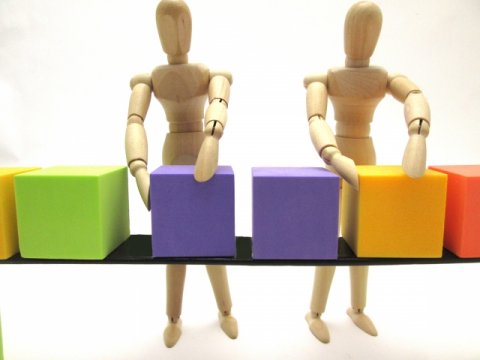
欲しい品物はスマホを操作するだけで購入出来るのが、今の世の中です。
また、手持ちの現金がなくとも、電子マネーや仮想通貨、クレジットカードなどで品物を買うことが出来ますから、現在は正に「買い物天国」とも呼べる時代でしょう。
しかしながら、買い物が身近なものになればなる程、そのリスクが高まるのが「不良品などに関する問題」です。
購入した品物が最初から故障していた場合などは、それだけでも嫌な気持ちになるものですし、商品の欠陥が原因で怪我をしてしまったり、損害を被った場合には、謝罪や交換だけでは、とても収まりが付きませんよね。
そこで本日は「PL法とは?わかりやすく解説致します!」と題して、メーカーが負う製造者責任について解説してみたいと思います。
スポンサーリンク
PL法って何だろう?
「PL法」という名称自体は「テレビの報道番組などで耳にしたことがある」という方が殆どであるかと思いますが、『一体どんな内容の法律なの?』と問われると、首を傾げてしまう方も多いことでしょう。
正式名称を「製造物責任法」というPL法は、平成7年に施行された法律であり、ユーザーから提起される、欠陥品に関する製造業者への損害賠償請求についてのルールを定めた法令となります。(因みにPLとはproduct liabilityの略)
こんなお話をすると、「欠陥品を作ったメーカーの責任を追及するのに、わざわざ新しい法律を作る必要があるの?」なんてお声も聞えて来そうですが、それまでの法律(民法)では、ユーザーが救済出来ないケースが多々ありました。
それというのも、民法で欠陥品によって受けた損害の賠償請求を行おうとすると、まずは被害者が製造業者に不法行為があったことを証明する必要が出て来ます。
また不法行為責任が生じるのは、製造業者に過失があった場合のみとなりますから、欠陥が生じた理由を追求し、相手の過失を立証しなければ救済を受けられないのが現実だったのです。
そしてこれでは、裁判に非常に長い時間と高額な費用が掛かる上、勝つ見込みも少なくなってしまいますから、あまりにユーザーが不利であると言わざるを得ません。
そこで政府はPL法を施行することにより、製造者に「不法行為責任」ではなく『製造物責任』を負わせ、「過失」ではなく『欠陥』を証明出来れば、損害賠償が可能となるシステムを作り上げたのです。
PL法の概要
前項の解説にて、PL法のおおよその主旨はご理解頂けたことと思いますので、本項ではより具体的な法律の内容に迫ってみましょう。
製造物の定義
その名の通り、この法律の対象となるのは製造物ですから、テレビやスマホなどの家電から、人形、自転車、机や椅子、果てはお弁当やケーキなどの食料品まで、人の手が加わってあらゆる物に適応されます。
但し、野菜や果物、魚まるまる一匹など、一切手を加えていない商品については適応除外となります。
また「動産であること」も定義されていますから、電気や光、電波などは対象外な上、コンピュータープログラムやアプリなども同様でしょう。
欠陥の定義
続いて「PL法の対象となる欠陥は何なのか?」という点について、解説致します。
一言で欠陥といっても、設計自体に問題がある場合から、使用されている部品に原因があるケース、また説明書に不備がある場合など、様々なパターンがあり得るでしょう。
更にはメーカーはしっかりと指示を出していたのに、組み立てを行った下請け業者の手抜きで問題が発生することもあるはずです。
こうした様々なケースを考えると、一体どこまでが製造者の責任の範疇であるか悩ましく思えて来ますが、消費者保護を第一に掲げるこのPL法では、先に挙げた全てパターンで「メーカーに製造物責任あり」との判断が下されます。
但し、あくまで「欠陥が予測出来た場合のみ」という前提が付きますから、『当時の科学技術では危険性が判らなかった』なんて場合には免責となるでしょう。
スポンサーリンク
製造業者とみなされる者
では、どんな立場にいる者が「製造業者」としてPL法の適応を受けるのでしょう。
まず原則として、事業として(反復継続して)製造を行った者が対象ということになりますから、例え個人で家具を作って販売した場合も、この法律の適応を受けます。
また、輸入品については輸入業者も対象となりますから、例え製造に一切係っていなくても、輸入販売を行っただけで責任を負うことになるのです。
更には、例え製造者でなくとも、製造会社と誤認される様な表示がされていた場合や、実質的に製造者の立場にあるだけで、責任を問われることになりますから、業者にとっては非常に厳しい法律と言えるでしょう。
PL法が適応される期間
この様に非常に厳しいPL法ですが、期間的な制限も設けられており、製品の引渡しから10年で除斥(時効の様な制度)となる上、実際に損害を受けた際にも、その事実を知った時から3年で損害賠償の請求は出来なくなります。(消滅時効)
PL法で訴訟となった事例
では具体的に、これまでどの様なケースで製造物責任が認められて来たのでしょうか。
「これぞ製造物責任」というステレオタイプな事例から申し上げれば、購入した脚立に欠陥があり怪我をした事例や、自転車のハンドルが折れ、重傷を負った事件などで、「製造物責任あり」という判決が下っています。
また判決にまでは至っていませんが(和解している)、某一口タイプの健康ゼリーによる窒息死事件でも、製造物責任の有無が問われました。
なお近年の訴訟例を見て行くと、意外にも「食」に絡んだ事件が多いのも特徴と言えるでしょう。
給食で提供されたオカズにより、O157の患者が出たケースでは製造物責任が認められましたし、漢方薬での健康被害、珍しいケースでは割烹で提供された魚料理による中毒などでも、「責任あり」との判決が下っています。
因みに、病院での治療器具や薬の欠陥や、エステサロンでの美容器具の不具合などの事例も少なくありません。
スポンサーリンク
PL法とは?まとめ
さてここまで、PL法についての解説を行って参りました。
家電製品に付いて来るマニュアルを見ると、「こんな事まで注意書きに書かなくても・・・」という様な警告が記されているのを見掛けますが、製造物責任を学ぶと、こうした記載がある理由が非常に素直に理解出来ますよね。
また、製造物責任は企業を相手取っての裁判となりますし、ユーザーに良心的な判決が出やすい傾向にありますから、PL法絡みでの訴訟は非常に件数が多いのが特徴です。
但し裁判所としても、あまりに多くの製造物責任を認めてしまうと、我が国の経済活動自体に支障を可能性がありますから、その判断は非常に慎重なものとなっています。
よって、言い掛かり的な訴訟では、まず製造物責任が認められることはありませんので、その点だけは是非ご注意頂きたいところです。
なお欠陥の原因がメーカーにはなく、販売店にあるケースも時折見受けられます。
例えば、小売業者が家電製品を雨に濡らしてしまったにも係らず、これを販売してしまい、電気系統のショートによって火災が引き起こされた場合などです。
こうした事例では、メーカーに対する製造物責任ではなく、小売店に対して不法行為責任を問うことになりますから、被害者には販売者の過失を証明することが必要となるでしょう。
ではこれにて、「PL法とは?わかりやすく解説致します!」の記事を締め括らせて頂きたいと思います。
スポンサーリンク
